お受け取り方法の概要(併給)
(1)「併給」のお受け取り方法について
これまで積み立てた資産を、一部を一時金、残りを年金で受け取る方法です(これを「併給」といいます)。
併給は、ご加入プランの規約等![]() に定めがある場合に限り選択することができます。
に定めがある場合に限り選択することができます。
- 国民年金基金連合会が作成している個人型年金規約や、個人型プランを実施している運用関連運営管理機関が独自に定めているお取扱い内容(運営管理機関の定め)を指します。
- ご加入プランの規約等の内容を確認される方は、運用関連運営管理機関の窓口にお問合せください。
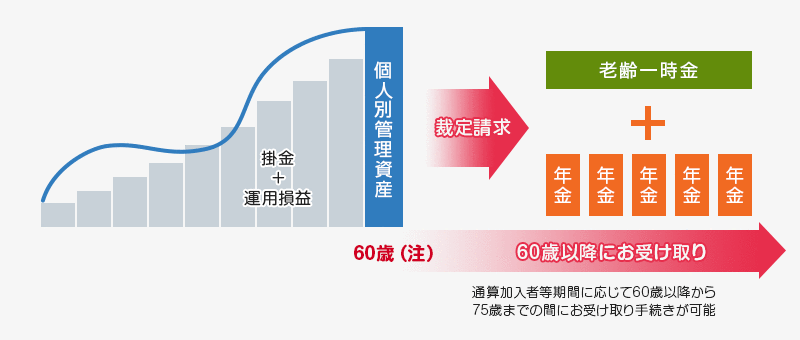
(注)2022年4月1日以前に70歳の誕生日を迎えられる方の請求期限は、70歳の誕生日の2日前までとなります。
(2)「老齢一時金」の税制上の取扱いについて
老齢給付金を「一時金」としてお受け取りになる場合、税務上は「退職所得」となり、税制上の優遇措置である「退職所得控除」が適用されます。
次の方法により計算した「所得税額」および「住民税額」を源泉徴収(住民税は特別徴収)したうえで、お振込します。
- 次の式で、「課税退職所得金額」を求めます。
課税退職所得金額=(その年の退職所得の金額の合計額![]() -退職所得控除額)×1/2
-退職所得控除額)×1/2
ワンポイント
退職所得控除額の計算方法
- 一般退職の場合の退職所得控除額は、下表の通りとなります。
- なお、同年および前年以前19年以内
 に、他の退職所得等を受け取られている場合、退職所得控除額の調整が行われます。
に、他の退職所得等を受け取られている場合、退職所得控除額の調整が行われます。 - 勤続期間が5年以下の場合、短期退職所得と見做されます。
短期退職所得については、短期退職手当として受け取った金額の合計額が300万円+退職所得控除額を超えていない場合、一般退職手当と同様、全て1/2課税となります。
300万円+退職所得控除額を超えている部分の収入金額は、1/2課税の対象になりません。
退職所得控除額は、一般退職の場合におけるものと同じ、下表のとおりとなります。
| 勤続年数 |
退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 ※80万円未満の時は、80万円 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
「前年以前19年以内」とは、例えば老齢一時金のご請求を西暦2026年に行う場合、西暦2007年から西暦2025年までの期間を指します。
※確定拠出年金においては、企業型年金および個人型年金の掛金の払込期間(確定拠出年金制度が導入された際に従前の企業年金等からの制度移行があった場合、その制度移行により算入された期間を含みます)が勤続年数とみなされます。
「確定拠出年金の老齢給付金(一時金)よりも前に受け取った退職金等の金額」と「確定拠出年金の老齢給付金(一時金)の金額」の合計額
- 上記計算式で求めた「課税退職所得金額」(A)をもとに、「所得税」および「住民税」を計算します。
(1)「所得税額」の計算は、下表に従って行われます。
| 課税退職所得額(A) | 所得税額の計算方法 |
|---|---|
| 195万円以下 | ((A)×5%)×102.1%(※) |
| 195万円超、330万円以下 | ((A)×10% - 97,500円)×102.1%(※) |
| 330万円超、695万円以下 | ((A)×20% - 427,500円)×102.1%(※) |
| 695万円超、900万円以下 | ((A)×23% - 636,000円)×102.1%(※) |
| 900万円超、1,800万円以下 | ((A)×33% - 1,536,000円)×102.1%(※) |
| 1,800万円超、4,000万円以下 | ((A)×40% - 2,796,000円)×102.1%(※) |
| 4,000万円超 | ((A)×45% - 4,796,000円)×102.1%(※) |
(※)2013年1月1日~2037年12月31日までの所得については、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます(計算式内下線部分)。
(2)「住民税額」は、「市町村民税」と「道府県民税」に分けられ、それぞれ以下の式に従って計算されます。
市町村民税=(A)×6% 道府県民税=(A)×4%
(3)「老齢一時金」にかかる各種手数料について
老齢一時金のお受け取りに際し発生する手数料は、次の通りです。
なお、当手数料のご負担者や金額は、ご加入プランの規約に定められています。
口座管理手数料(運用指図者の月次手数料)
老齢一時金を受け取るまで毎月所定の金額が発生します。
給付手数料(振込手数料)
資産管理機関が、ご指定の金融機関口座に老齢一時金をお振込の際、所定の金額が1回のみ発生します。
(2)「老齢年金」のお受け取り方法について
年金のお受け取りにあたっては、その具体的なお受け取り方法詳細について、ご加入プランの規約の範囲内で、自ら指定する必要があります。
あなたが選択可能な「老齢年金」のお受け取り方法は、以下の通りです。
①「分割取崩年金」によるお受け取り
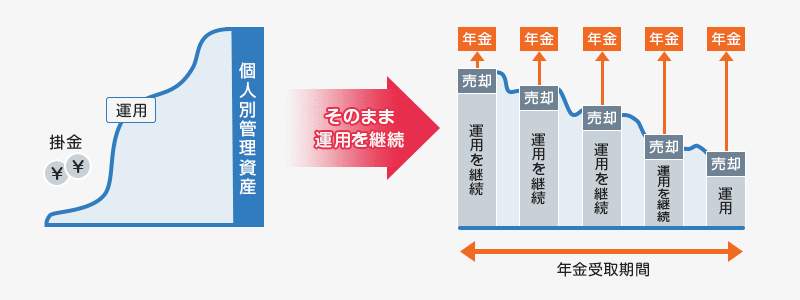
<こんな方におすすめ>
- ご自身で運用を継続しながら、年金を受け取りたい方。
<受け取り方法>
- 保有している個人別管理資産を現金化(資産を売却)して、年金を受け取る方法です。
<主な特徴>
- 受取期間中も、ご自身で運用を続けることができ、その運用結果により受取総額が変動します。
- 受取期間中に亡くなられた場合、残りの年金資産は「死亡一時金」としてご遺族に支給されます。
ワンポイント
年金額の算出方法について
1回の支給でお受け取りになる年金額の算出方法は、ご加入プランの規約により予め定められた「基本支給方式 」と、規約の範囲内でご自身が指定した「年金額の算出方法
」と、規約の範囲内でご自身が指定した「年金額の算出方法 」によって決まります。
」によって決まります。
②「年金商品(年金給付専用商品)」によるお受け取り
A.「確定年金」によるお受け取り
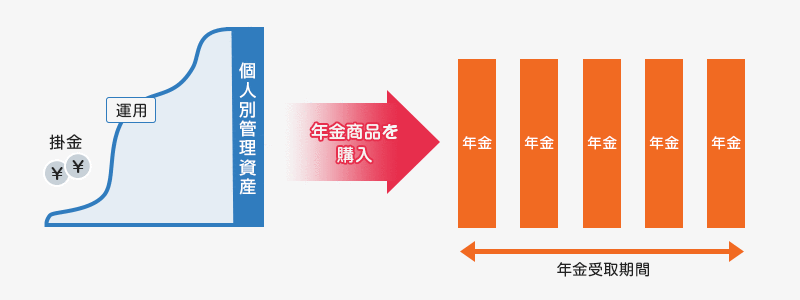
<こんな方におすすめ>
- 毎回決まった年金額を一定の期間で受け取りたい方。
<受け取り方法>
- 年金開始時に年金商品(年金給付専用商品)を購入します。
- 年金の金額は、生命保険会社等で計算されます。
<主な特徴>
- 年金商品を購入した後は、他の商品へスイッチングを 行うことができません。
- 受取期間中に亡くなられた場合、残りの期間に応じた 所定の金額が「死亡一時金」としてご遺族に支給されます。
B.「終身年金」によるお受け取り
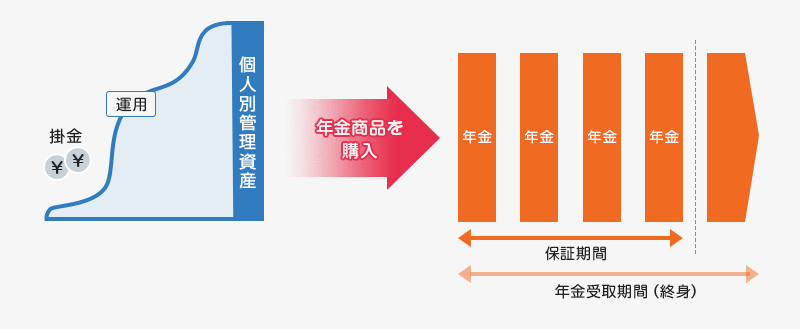
<こんな方におすすめ>
- 毎回決まった年金額を終身(生涯にわたって)で受け取りたい方。
<受け取り方法>
- 年金開始時に年金商品(年金給付専用商品)を購入します。
- 年金の金額は、生命保険会社等で計算されます。
<主な特徴>
- 年金商品を購入した後は、他の商品へスイッチングを行うことができません。
- 保証期間中に亡くなられた場合、残りの保証期間に応じた 所定の金額が「死亡一時金」としてご遺族に支給されます。
ワンポイント
ご自身が指定可能な年金受取方法の確認方法について
JIS&Tより送付された「年金受取方法の指定書」がお手元にある方は、指定書の表示内容をご確認いただくことによって、ご自身が指定可能な年金受取方法を把握することができます(「年金受取方法の指定書」は、ご加入プランの規約の取扱いに合わせて、指定可能な年金受取方法のみを印字して送付しています)。
※「年金受取方法の指定書」を含めた必要書類の入手方法については、「【Step2】必要書類の入手」の詳細ページをご参照ください。
※「年金受取方法の指定書」の記入方法等については、「【Step3】必要書類の記入・提出」の詳細ページをご参照ください。
(3)「老齢年金」の税制上の取扱いについて
老齢給付金を「年金」としてお受け取りになる場合、税務上は「雑所得」となり、税制上の優遇措置である「公的年金等控除」が適用されます。
年金のお支払いの際は、次の式で計算した所得税を源泉徴収したうえで、お振込します。
源泉徴収税額=(年金の支払額 -(年金の支払額×25%))×10%×102.1%(※)=年金の支払額×7.6575%
(※)2013年1月1日~2037年12月31日までの所得については、所得税に2.1%を乗じた復興特別所得税が、所得税にあわせて源泉徴収されます(計算式内下線部分)。
ご注意ください!
確定申告について
老齢給付金を「年金」でお受け取りになる場合は、確定申告で精算することとなります。
(上の式で求めた源泉徴収税額は確定した税額ではありませんので、雑所得として他の所得とあわせて確定申告を行い、過不足を精算することとなります。)
確定申告の際には、毎年1月中にJIS&Tからお送りする「公的年金等の源泉徴収票」をご使用ください。
ワンポイント
年金にかかる税金
その年にお受け取りになった年金(公的年金や確定拠出年金を含む企業年金)については、お受け取りになった年金の合計額から「公的年金等控除額」を差し引いた額が雑所得の金額となります。
雑所得の金額=お受け取りになった年金の収入金額(税引前)- 公的年金等控除額
【公的年金等控除額】
| 年齢 | 年金の収入金額(a) | 公的年金等控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
| 330万円超、410万円以下 | (a)×25%+27.5万円 | (a)×25%+17.5万円 | (a)×25%+7.5万円 | |
| 410万円超、770万円以下 | (a)×15%+68.5万円 | (a)×15%+58.5万円 | (a)×15%+48.5万円 | |
| 770万円超、1,000万円以下 | (a)×5%+145.5万円 | (a)×5%+135.5万円 | (a)×5%+125.5万円 | |
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
| 130万円超、410万円以下 | (a)×25%+27.5万円 | (a)×25%+17.5万円 | (a)×25%+7.5万円 | |
| 410万円超、770万円以下 | (a)×15%+68.5万円 | (a)×15%+58.5万円 | (a)×15%+48.5万円 | |
| 770万円超、1,000万円以下 | (a)×5%+145.5万円 | (a)×5%+135.5万円 | (a)×5%+125.5万円 | |
| 1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
上記の公的年金等控除額は、2020年分以降の所得税について適用されます。
年金のお支払い時に源泉徴収される税金は所得税のみで、住民税は対象となりません。住民税については、翌年度に市区町村より通知されます。
(4)「老齢年金」にかかる各種手数料について
老齢年金のお受け取りに際し発生する手数料は、次の通りです。
なお、当手数料のご負担者や金額は、ご加入プランの規約に定められています。
口座管理手数料(運用指図者の月次手数料)
老齢年金のお受け取りが終了するまで毎月所定の金額が発生します。
給付手数料(振込手数料)
資産管理機関が、ご指定の金融機関口座に老齢年金をお振込の際に、毎回所定の金額が発生します。
